3つの生息条件が揃えばブラックバスは生息できる!
ブラックバスを釣る上で、「この湖や野池はバスが生息しているのかわからない」と言う疑問が生まれます。
僕も初めての場所ではそうでした。
釣れない人ほど、ブラックバスを探すことが出来ずに、疑心暗鬼になりながら、ルアーを投げ続けます。
ブラックバスが目視できなければ、釣りをするしかありませんが、魚が生息する条件・生態の知識があれば、もっと状況確認が早くなります。
場所を探すヒントになればと思いこの記事を書きました。




また、現在バスが生息しているフィールドでも、バスのいる場所を探すヒントとなる内容でもありますので、ぜひ参考にしてください。
かなりの数の文献を参考にしています。
バス釣りをする方は、最後までご覧頂くことを強くおすすめします。
※使用写真は全て自分で撮ったものです。
今回はラージマウスバス(日本のほとんどのブラックバス)を対象とした内容です。

そして、ブラックバスの本場、アメリカの研究チームが導き出した基本的な生息条件となります。
①水温
ブラックバスの適水温と生息水温
バスの行動研究から最も好きな水温は22℃から27℃ほどと言われます。
日本でいうと場所や季節によりバラバラだと思いますが、この水温であればブラックバスが活発に餌を追ったり行動できると考えてまず間違いありません。
そして、生息できる水温は3.2℃から38.5℃と非常に幅が広いです。
※バス釣りする人こそ、水温計を購入することを強くオススメします。
そのため、バスの東北の寒い地域で育った個体と九州の比較的温暖な水温で育ったバスでは、行動に違いは出ます。
簡単に言うとバスも住んでいる地域の水温に慣れているのです。
現に山梨県の河口湖では、水温2℃で大型のブラックバスが泳いでいるのを発見している方を何人か知っています。
つまり環境に適応してる強い個体も存在し、数字が絶対ではないことが言えます。
それに、実際の釣り場では理想の水温であっても魚が居ないことがあります。
そう言った場合、例え好む水温を下回る場所であっても、本能的にカバー(物陰を作る場所)などの太陽の光を避ける場所に隠れていることが多いです。
ブラックバスの水温別のおおよその行動
水温によりおおよその行動を書くとこんな感じになります。
○22℃から27℃は比較的動きやすく、活動的。それ以外は個体の大きさや体力で異なる。 ○表水温が10℃以下になると行動が鈍くなる。 ○5℃以下になると捕食も週一ペースになるなど、著しく行動しなくなる。 ○夏は27℃前後を超え出すと快適な場所を求めて深場、水温の低い流れのあるとこ、物陰に行ってしまう。
ブラックバスは、年中釣れる魚
なぜなら、僕は比較的気温の低く寒い東北でも、年中バスを釣りました。
本当に厳しいと言われる二月でもタイミング次第で魚は釣れます。
ブラックバスが生き残れない水温
しかし、問題は38℃以上になった時です。
温度が高すぎるとブラックバスは基本的に生き延びることができません。
真夏の太陽ガンガンの日などが続くタイミングで、40℃近くの水温であれば釣り場を移動するか、温度が低い場所を探す必要があります。
バスも本能的にその場に居たがらないのです。
②酸素量
ゲームフィッシュの中でも酸素量を多く消費
ブラックバスは、他の魚種に比べて多くの酸素量を必要とする魚種です。
例えば、どの湖でも浅場がありそこには十分な酸素量があります。
そのため、浅場にバスが寄っているのはそういった理由もあるのです。
大きな個体ほど、岸側を好むと各有名バスプロが言っているのも頷けます。
これは、酸素量が多いと言う理由で岸にいることも多いためです。
簡単に言うと、浅場はブラックバスの呼吸が楽なのです。
流れがあると酸素量が多い
さらに、流れがあると酸素も多いため魚は呼吸が楽になります。
そのため、流れがある程度あることも生息しているか確認するポイントになります。
また、池などの水をみて変な泡が浮いていたり、淀んでいる水が溜まっている場所はバスが呼吸しにくいため、移動している可能性があります。
普段釣りをしている場所でも水をみて淀んでいたり、水の動きがなく泡が浮いている場所は魚が離れてしまっている可能性が高いのです。
水生植物も大きなヒント
酸素量の多い場所の例として、ウィード(水生植物)が多いところが考えられます。
びっしり生えて居たら、酸素量が多いので魚も多い可能性が高いです。
ウィード(水生植物)があるということは栄養が多いと言うことですので、生き物も集まります。
そのため、餌も多くなりブラックバスも寄りやすくなるのです。
プランクトンが多いところは注意が必要
栄養が多すぎる湖も酸素量が少なくなります。
栄養が多いと光合成をするプランクトンが増えます。
プランクトンがいること自体は良いことですが、問題は死んだ時です。
プランクトンが底に沈みだして腐敗していく過程で多くの酸素を消費します。
膨大な量の酸素が消費されるため、深場がブラックバスの生息に適さなくなります。
プランクトンが多いかどうかも1つの目安になります。
見分け方ですが、緑色になり、どよんとしている水が特長です。
余談ですが、大きなブラックバスはエラが弱いです。
そのため、酸素量が十分でなければ、行動しません。
酸素量が少なくなる要因として、水がどよんとしていること、流れがないこと、プランクトンが多すぎること、水生植物が少ないことなどなどです。
ビックフィッシュを多く釣るバスプロはほぼ例外なくこう言った知識を持っており、酸素量と言うのも意識して釣りをしています。
なぜなら、大型の魚の居場所がわかりやすい目安だからです。
③着き場
ブラックバスの着き場を理解するための主なワード
○カバー(物陰を作る物体) 例:ハスなどの浮き草、岸まで垂れ下がる木 ○ストラクチャー(バスが一時的に着く水中の地形変化) 例:水中のかけ上がり、かけ下がり(水深が変化する場所)、チャネルと言われる溝、レイダウン(沈んでいる木)、地質が変化する場所など ちなみに杭などの縦に伸びているストラクチャーを「縦スト」と表現したりします。 縦ストでは斜めになっている部分やその影がポイントになることが多いです。 ○マンメイドストラクチャー 例:コンクリート岸のえぐれ、消波ブロックなど 











ブラックバスは水中の様々な変化を着き場として利用します。
なぜなら、鳥や自分を襲う可能性がある生物が本能的に怖いのです。
3つの条件の中で目視で魚を発見しやすい条件でもあります。
また、このストラクチャー(バスが一時的に着く水中の地形変化)に着くと言う習性はブラックバスを釣る上で最も重要なこととなります。
最強なのは、ストラクチャー(バスが一時的に着く水中の地形変化)とカバー(物陰を作る物体)が複合している場所です。
こういう場所は釣りをするなら、絶対狙っておきたい場所です。

この知識があれば、木だろうと、水草だろうと、コンクリートだろうと同様の考えができます。
あくまで基本的な考えですが、これが基礎となることは間違いありません。
断言しておきます。
なぜ、基本となるかと言うと、ラージマウスバスの場合、日常的に道しるべとして、このようなストラクチャーを利用しながら生活しているためです。
人間で例えると、歩道を歩いているようなものです。
さすがに車通りの多い道路は歩きませんよね?
魚からしたら、それくらい当たり前の行動なのです。
ラージマウスバスは生まれた時からカバーが必要
実はラージマウスバスの稚魚は生まれた瞬間にカバーに着いています。
そうして集団で、群がっているのです。
その後、少し成長していくに従い、ストラクチャー付近やカバーに散って行くのです。
構造的に変化のない場所では?
構造的に変化のないエリアと言うものがあります。
そうした場合、何を見るかと言うと色の変化している場所だったり、一本だけある草などちょっとした変化を見つけてください。
水の色などちょっとしたことがバスを探す上で非常に重要なことに繋がります。
水中、そして岸辺の変化を見つけることが大事です。
また、全国的な野池では上記の基礎を当てはめると共通して良いポイントは四つ角です。野池の場合、この四角は外せませんね。
最後に
このように水温、酸素量、着き場を意識することで、なぜここに魚がいるのか説明できるようになったのではないでしょうか?
こう言う知識こそが、ゲームフィッシングとしてバス釣りを面白くするのです。
ルアーや道具も非常に重要ですが、こうした魚の特長や生態を知ることが一番先です。
優先順位が一番高いと言えるでしょう。
バスを釣る上で必要な知識は膨大ですが、基礎が一番です。
また、1つアドバイスさせて頂くと、釣り日記をつける際はこれらの条件を元に、ポイントの特徴と水深、水温を記録しておくと後々役にたちます!


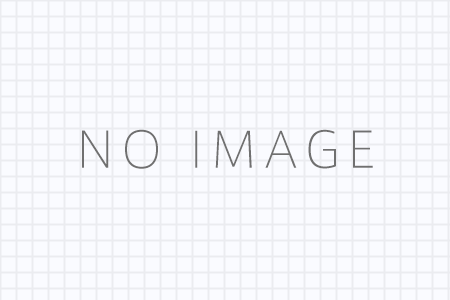


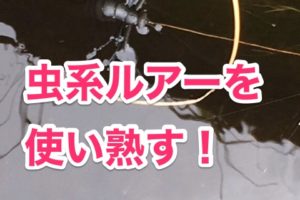
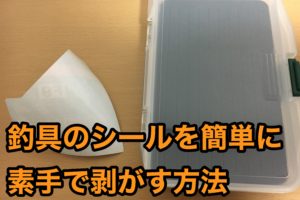

コメントを残す