最近、少し気候変動が多く感じられません?
例えば、梅雨がはじめろうとしているのに、少し肌寒いとか、雪が多かったり、少なかったり、暑い日にちが長引いたり・・・
地球は少しずつ変化しているようです。
あと数年もすれば、もしかしたら気温が今現在の状態ではなくなるかもしれません。
これは僕たちの気温以外にも海水温の変化としても現れはじめています。
その証拠に、最近は関東でオオモンハタがどんどん出現し始め、キジハタが全国各地に現れはじめました。
これが何を意味しているかというとハタの勢力図が変わってきているということです。
どんどん勢力を拡大していますね。
今回はこれからのロックフィッシュゲームについて、未来の話をしようと思います。
ハタの基本的な生存戦略
特定の種類を指定せずに、他のロックフィッシュとは明らかに違うハタの生存戦略についてお話します。
カサゴなどの魚は、あまり動かずに目の前にきた餌だけを捉えて生活しているザ・ロックフィッシュと言える生存戦略をとっています。
あまり動かないので、餌も多く獲れない代わりに敵に見つかりにくいというメリットがあるのです。
一方ハタ類は別の戦略をとっています。
効率よく産卵するために、性転換を行うのです。
また、移動して多くの餌を食べて、いち早く成長し、子孫を残します。
ハタ類は全国のカサゴやメバル、ソイ類、アイナメなんかと比べるとかなりのスピードで子孫を残して、成長し続けることができるのです。
すごい!
そのため、たくさんの餌が必要になり、必然的に移動して餌を探るようになります。
大きくハタが移動してくる根本的な理由です。
デメリットとして、外的環境に左右され、餌が取れないと餓死してしまうリスクがあり、また、常に移動中は他の魚に捕食されてしまうリスクもあります。
ブラックバスと比較される方もいると思いますが、ハタ類は明らかにバスよりも繁殖力が強く、ストロングです。
そのため、ハードルアーやソフトルアーで狙う魚の中でもかなり強い部類の魚だと言えます。
伊豆船宿の話
静岡の西伊豆にいつもお世話になっている船長さんがいるのですが、その船長さん曰く「オオモンハタは10年以上前から急に増えはじめた」と言っていました。
また、話を詳しく聞くと、こんなにも増えた魚は初めてだと言っていました。
しかも、年々増加傾向のようです。
関東では、アカハタも徐々に姿を現し、ある時期には知る人ぞ知る魚となり、徐々に認知されていきました。
今では当たり前に認知されている魚となりました。
最初は船でのカワハギ釣りやカサゴ船に混じる程度だったようですが、その繁殖力でカサゴを凌駕するスピードで釣れ始めたのが、ここ数年とのことです。
それだけ、ハタの生存戦略はスピーディーだとも言えます。
この大きな変化の原因を今回は探ってみたいと思います。
ハタ類の移動には法則がある
いろんなハタの生息範囲の地図を眺めていたら、こんなことがわかってきました。
・太平洋側に関しては沖縄からカンモンハタなどのハタ類全般。
・九州から 関東伊豆半島、相模湾まで主にオオモンハタ、アカハタが生息。
・日本海側は九州を超える辺りまではアカハタ、キジハタ、マハタが生息。
・しかしそこを境にキジハタ、マハタのみの生息となり最北端だと青森県までキジハタが生息しています。(日本海側が中心)
・最近だと東京湾・陸奥湾(青森県)・北海道日本海側までキジハタが現れる。
・マハタに関してはポツポツと、日本列島全体にいる珍しいハタ。
神奈川県大磯周辺では最近マハタを専門に狙う釣り人まで現れはじめたようです。
数年前には全く姿を見なかったと言いますからすごい移動スピードです。
近年、このようにハタの生息域が拡大されつつあり、ハタが大きく移動する魚だということがわかってきました。
ハタは潮の影響を受ける地域に沿っている?
まずこちらの写真を見ていただきたいです。
引用サイト:海ごみ「海ごみと海流」
これは黒潮の強さを矢印の太さで、矢印の長さで黒潮の動きを表したものです。
黒潮は毎年変化するものですのでこの図が正しいとは言えませんが、この図を見てピンとくる方も多いと思います。
この地図は、移動したハタ類の生息域とぴたりと重なるんです!
つまり、黒潮の影響を強く受けるエリア(日本海側は対馬海流として)がハタの生息を確認できるということになりますから、おのずとハタの生息可能地域が絞られてきます。
親潮がメインの三陸にはほとんどハタ類が移動しにくいことがわかります。
しかし、キジハタが乗ってきた対馬海流の一部が三陸にも流れています。
その証拠に三陸(東北)でもキジハタが発見されています。
アイナメと一緒に水揚げされたキジハタが1尾。
このキジハタは金華山方面の網で獲れたそうです。
金華山とは宮城県牡鹿半島の沖合いにある島のことです。
つまり、今後、潮に乗って三陸もハタ類が侵入してくる時代がくるのも時間の問題であると考えています。
そして、黒潮の影響を受ける相模湾も今後、可能性があるということでもあります。
神奈川県の大磯で釣れているマハタが良い例で、今後の兆候とみています。
追記:アカハタが川崎新堤で釣りあげられ、オオモンハタが相模湾で確認されました。(2019年冬)
また、僕は実際に東京湾でキジハタを釣っています。
詳細な場所は書けませんが、数年前からすでにここまでハタが移動してきているということです。
これからハタゲームの本格的な歴史が始まると予想しています。
北海道は本当の意味でのロックフィッシュ天国に?
さて、アイナメやクロソイ、貴重なシマゾイなどで有名な北海道ですが、再度下記、図をみてください。
引用サイト:海ごみ「海ごみと海流」
青森県の三沢漁港などを中心にキジハタが、かなりの数釣れています。
これは明らかに、対馬海流に乗ってきた証拠であり、今後もその生息域は広がっていくものとみています。
この図をみて思う方もいると思いますが、北海道にも対馬海流の一部が流れているのです。
何が言いたいのかと言うと、これまで釣れていたロックフィッシュにキジハタがどんどん加わっていき、北海道ではアイナメ、ソイ、メバル、ハタと全国のロックフィッシュ全てが釣れる時代がくると予想しています。
ある意味、凄い時代です。
こうしてあなたがこの記事を読んでいる間にも、確実にハタ類は移動をしています。
ハタ類は大きく移動すると言う認識を持っていないと、いけません。
間違いなく、最初にそのポイントを発見した釣り人は美味しい思いをするでしょう。
[aside type=”warning”]
※とある方からの情報で北海道の日本海側でキジハタが釣れはじめたという情報をキャッチしました。
キジハタが日本海に多く生息していることは有名なお話ですが、まさか北海道まで上がってくるとは…
[/aside]
数年前からメーカーを中心にこうした情報が広がり、ハタブームを作ろうとしていました。
その背景には、こうしたハタの生息域の変化と言う海の変化が隠されています。
今は九州のシェアが圧倒的なようですが、いずれは東北や北海道の人もハタゲームに目覚めると感じています。
この時代の変化の節目に、どんな準備をするかで、釣りの楽しみが変わります。
ぜひ、気になる方はハタという魚を一度調べてみてください。
すでに釣ったことのある方は、よりハタの習性を追求していけたら良いですね。
アングラーが意識すること
具体的にどうしていけば良いのですか?と質問があると思いますので回答します。
それは、スイミングの釣りを増やすことです。
ハタがいないと言われている地域でもスイミングの釣りからはじめるのです。
もちろん、スイミングの釣りは状況がマッチしていなくては釣れません。
しかし、東北や北海道の人に多いのですが、テキサスリグで岩をネチネチ探る釣りしかできない人がいます。
そのため、既存の釣り方に固執せずに、浮かす釣りを実践していった方が良いと思います。
アイナメと同じ感覚で釣りをしていると、本当に小さい魚しか反応しないケースが多いです。
そのため、浮かしてハタに発見させて食わせるという釣りをした方が良いと思います。
全部の釣りでするのではなく、釣り場について15分だけはスイミングの釣りに徹するとかでも良いと思います。
とにかく、東北や北海道の人がしている既存のボトムバンプやリフト&フォールはハタが反応しにくいです。
ハタがいるかもしれない前提で釣りをしてみてください。
可能性が限りなく低いかもしれませんが、発見すれば自分だけウハウハな釣りができます。
最後までご覧いただきありがとうございます。



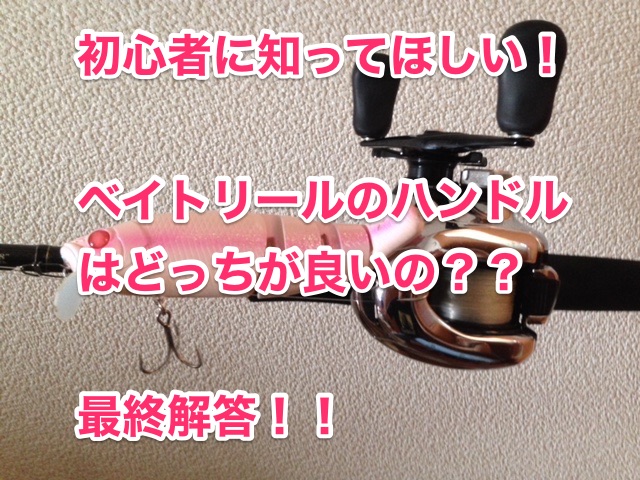





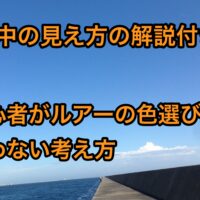


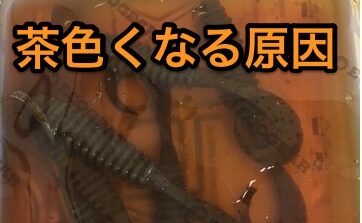


東伊豆稲取にボートを置くアングラーですが1つテンヤに甘エビを付けて30cmのアカハタを数匹釣り知合いの漁師さんに驚かれ家で食べるから3匹分けてくれと分けたのが3年前。
一昨年、去年はアオハタ、キハタが多かったのだが、今年はアカハタが凄まじく増えたと言うか殆どアカハタ。ハタ類の中でも特に活発、獰猛なのか底から5mの上針や仕掛けの回収中でも中層で喰って来ます。今や水深3mから60mまで喰えばアカハタでホウロクが少なくなりました。想像ですがカサゴや他のハタの稚魚、卵をアカハタは食べていませんか?そのくらい凄い勢いです。海老網にキジハタのデカイのも入りました❗️
アカハタが増えてマダイが釣れなくなってきてる気が凄くします。やはり襲っているのでは?