ハタは学習していくことを考えれば、釣り方も一筋縄ではいかず、アングラー側が色々と模索し、食性や条件反射(リアクション)で魚に口を使わせる方法も日々進化させていかなくてはいけないとあらためて感じています。
ロックフィッシュゲームにおいて、テキサスリグは有効なリグに間違いないですが、ハタの生態を知れば知るほど、別のルアーが有効だと考えられる部分がまだまだあります。
個人的にはロックフィッシュゲームという括りにハタを入れてしまうのはちょっと違う気がしています。
従来のロックフィッシュの特性とハタは別の生態を持っているので、ハタゲームと表現する方が正しいのではないかと感じています。
ロックフィッシュ=根の周り=引っかからないテキサスリグみたいな構図ではなく、ハタはどのように生活し、どう捕食しているのかを知ることで別のルアーの可能性が浮上してきます。
例えば、岸からのスローピッチジャークなんかは、ハイピッチなジグのジャークでは反応しない待ち伏せ型のハタが結構ヒットしてきます。
スローピッチジャークは、ヒラヒラと落ちていく小魚を模した動きを演出するため、ベイトを追う魚がいれば効果抜群です。
これから岸からのスローピッチジャークの有効性はどんどん証明されていくと考えていますし、メーカーから最近岸からのジグがどんどん発売されています。
そして、ジグと言えばジグとオフセットを付けたジグリグ!
佐藤文紀さんが提唱したリグですが、当時は本当に使えるのかな?と思っていました。(佐藤さんごめんなさい)
でも、ハタという魚を調べれば調べるほど、可能性のあるリグだと再認識しています。
ハタという魚はスズキ目の魚で、スズキに近い魚であると、佐藤文紀さんはおっしゃっています。
スズキ、つまりシーバスを東京湾なんかで狙おうとするとジグの後ろ側にフックを付けます。
なぜなら、ジグの頭や真ん中に食いにくる魚と違い、フォールの時に食ってくるため後ろにフックがないと掛かりが悪いんですね。
ハタはシーバスに限りなく近いことを考慮すれば、ジグのフォールをワームの抵抗で遅くして、かつジグの後ろ側に食わせのワームが付いているというリグは有効であると言えます。
問題は、ジグリグに対応しているジグを見つけられるかどうか。
通常のジグはフォール姿勢が決まっていて、ワームをつけることで本来の動きが殺されてしまう可能性が高いのです。
また、さらに変化することはフォール時間。
ジグで魚がバイトする際にキモとなるフォール時間は元々のルアーに組み込まれていますが、ジグとワームをつけることで、釣れるフォール時間を壊してしまう可能性が少なからずあるのです。
反対にフォール時間を調整し、釣れる時間を見つけることが出来る人は良いのですが、魚が反応する動きやフォール時間を見つけるまで、相当数のジグとワームで研究しなくてはいけません。
その作業を繰り返していけば、自分だけの魚に一歩近づくことが出来ますが、サンデーアングラーがやってしまうと迷宮入りしてしまうリスクも存在します。
誰もが魚を釣りたいものですが、釣れるかわからないルアーを投げ続けることほど辛いものはありません。
釣れないルアーで釣れるイメージを持って釣り続けるのには限界があると感じています。
スピナーベイトなんかは飛距離こそ出ず使い勝手が悪い面もありますが、目の前でリアクション的な釣りをするのには1番適していると思います。
釣り仲間からスピナーベイトでキジハタをボコボコに釣っていた話を聞いて、やっぱ有効なんだなぁと思いましたね。
ただし、スピナーベイトは飛距離の問題があったりしますし、何よりシーバスに有効なリグではないという点が気になります。
バイトミスが多いんです・・・・
佐藤さんが動画が言っているように、ハタは根回りにいるスズキというイメージを持った方が良いと思います。
スズキに有効なリグはハタ類にも効果的なはずです。
そのため、ハタゲームアングラーが参考にすべきは、過去のロックフィッシュという概念ではなく、シーバスのルアーフィッシングに隠されていると思うのです。




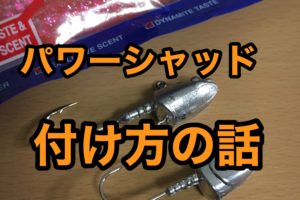


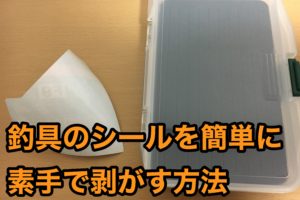



コメントを残す