ロックフィッシュアングラー必見のジグヘッドリグについてです。
なぜ、ジグヘッドは軽くて小さい方が良いのか?
古い記事にはなりますが、2016年12月号のSALTWATERからエコギアプロスタッフの折本さんの記事を引用して解説します。
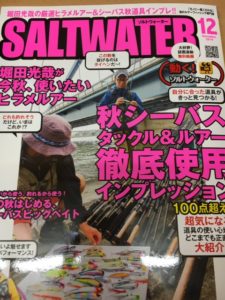
題:ソフトルアーの硬派な話 第11回小さく軽いフックというのが折本流
まずは、記事から抜粋。
「まず、ゲイプは小さめ。チヌとかアイナメは、突っつくようなバイトが多くて、そんなバイトをかけるには、より小さい方が有利です。ハタとかソイは吸い込み系のバイトですが、それでもブラックバスほどバフって吸い込むわけじゃない。だから、バス用よりは小さめで良い。」
なるほど!アイナメを狙うときは口腔内の関係上小さく、というのが僕の考えでしたが、アイナメ用に小さくセッティングしたリグでソイやハタをかけてもバレることも少ないですし、むしろワームの可動域が広がる分アピール力があがるんじゃないかと思ったりして…
ゲイプ幅に関しては、正直どれくらいの太さのあるワームを使うかによって変わると思うので何とも言えないですが、折本さんの言う通り、よりなるべく小さめを選ぶというのも1つの選択肢として考えて良いですよね。
あとは、針の太さ。
この記載にはありませんが、「なるべく細軸で」というのが折本さんの考えです。
細いPEを多用する折本さんはそれに合わせ針も細くという考えなのだと思います。反対に針が太い場合は、太めなPEが強度的にもベストセッティングになってきますね。
ノリーズからオーバルテンヤという製品が出ていますが、一般的なテンヤに比べ針が短く細いです。こういった製品からも折本さんの意思が伝わってきますね!
釣具屋時代に、オーバルテンヤをはじめて店頭に仕入した時の話ですが、「こんな細軸でタイ釣り大丈夫なのだろうか?」と一瞬焦りました。
他のダイワやジャッカルなどの製品に比べて明らかに細軸で、「タイに噛み潰されやしないか?」と言う印象でした。
しかし、実際に南房で使ってみると針が曲がるどころか、フッキングがよかったですね。
昔の時代の針感覚を今の時代に持ち込むのがいかに非常識かがよくわかりました。
昔の針は削って作っていた関係上、太くて強い針じゃないと魚の口腔内に刺さらなかったのかもしれません。
針先が今のフックに比べて甘いので、必然的に刺さりが悪く、針の懐まで貫通せずに負荷がかかり針自体が曲がるリスクがあり、太軸にせざるを得なかったということ。
今はほぼ全て化学研磨で作られていますから、針を研磨することはむしろ針をダメにしますよね。
つまり、今の化学研磨の針の方が刺さりが良い。
だから、思いっきり伝統的なデカ針、太軸のテンヤをやめて、「小さな針、細軸というスタイルが確立できたのではないか」と思えてなりません。
ただし、テンヤ真鯛をする時に、針が小さいと海老がとれやすいというデメリットがありますが、ワームと組み合わせることで真価を発揮するのがオーバルテンヤかもしれませんね。
海老がとれやすいことを考慮したのか、Lサイズのフックも発売されています!
もう一文。
「ジグヘッドの重さに関しては重すぎないこと。これはジグヘッドのデザインというよりどの重さを選ぶかということですが、シンカーが一体型のジグヘッドは、頭を振られた場合にどうしてもテコの原理で外れることが多いので、バレを少なくするには軽い方が有利。」
これに関しては非常によく頷けます。
オオモンハタゲームの際に水深40メートル前後を攻めるシチュエーションがありました。
僕は40グラムのジグヘッドにPE0.6号というセッティングで臨んでいました。
その際に5ヒット、3バラしという悔しい思いをしたことがあります。
原因はタックルのバランスでした。
ジグヘッドが潮の流れに対しては重すぎて、かつ細いPEを使ったことにより、水圧の抵抗を受けにくい状態(つまり、水を糸が切りやすい状態)でさらにジグヘッドが重いことで魚が自由に首を振ることが出来たという点がバラしの原因なんだと理解していました。
まさに折本さんはそのことをおっしゃっています。
最後に。
「作り手側はバランスを考えてデザインする。自分が手間暇かけて作った料理を、美味しく食べてくれよって感じですかね。その料理にケチャップかけたら台無しだよ、みたいな。ケチャップ味が好きな人はそれでいいのかもしれないのですが。」
最後は例え話が入っていますが、要は最高のセッティングを考え、試した状態で販売しているので「まずはそのまま使って下さい」という意味でしょう。
最終的にはバランス。
その見極めができるようになるまでは一旦、メーカーのテスターさんのモノマネをすることが一番釣果に繋がるのかも知れませんね。
僕なんかは、ルアーデザイナーがどんなことを意識して作ったのかを小さな水槽で試し泳ぎさせたりしますけど、結局わからないことも多いです。
でも、少しでも理解しようとすることで自分のタックル全てを見直し、自分のバランスを探すように心がけています。
ワームのサイズに合わせたフック選び
今回の話はワームに対して小さめという意味であり、決してなんでもフックサイズを小さくすれば良いという話ではありません。
例えば、下の写真では同じウエイトのジグヘッドですがフックサイズが違います。

もし同じサイズのワームをつけ、バランスが良いようなら小さめのサイズを選びます。
しかし、ワームとのバランスが悪い場合はしっかりフックサイズを使い分けしなくてはいけません。
例えば、写真上のサイズのフックの場合、グラスミノーのLをつけるとバランスが良いです。
しかし、下のサイズのフックにグラスミノーLをつけると針が小さすぎて針がかりしにくくなり、ショートバイトの原因になります。
反対に言えば、グラスミノーのMサイズはどちらのフックサイズも対応しています。
その場合、フックサイズを使い分けするなら、小さい方を選ぶという感じになります。
そのバランスはしっかり考えてセットしましょう。
目安として、ワームの長さの「1/3〜1/2」くらいの大きさの針を選ぶと間違いないでしょう。
ジグヘッドの針は魚には見えているのか?
色付きのラインを使った時によくある現象がありますが、ベイトフィッシュの群れにジグヘッドをキャストした時に謎のアタリがあることがあります。
トゥンっという小さなアタリ。
最近、この謎のアタリの正体がわかりました。
以前、クリアな海でPEラインに寄ってくる小魚を見ていた時の話です。
なんと、結束部分やPEラインの色付きの変化の場所に小魚がバイトして来ていたのです。笑
これにはかなり驚きました。
魚は色を認識していることは知っていましたが、まさかこんな小魚が結束部分や色の変化を見分けているとは思わなかったからです。
タチウオ釣りでもワイヤーなどの結束部分やラインを噛まれるという話はよく聞きます。
つまり、魚にもラインの色や太さは認識できているということ。
では、針はどうかと言えば、針も魚には認識されていると思います。
特にジグヘッドをボトムに置いた時なんかは大きな針だと、魚に見切られてしまう原因になりかねません。
意外な話かもしれませんが、魚には針は認識されていると思っています。
なぜ、そんな見えている針に魚が食いついてくるのか?
その答えは、「魚が食べたいという欲求に負けて冷静に判断できなくなっていたり、条件反射的に体が動いてしまった時」にルアーに魚が飛びつくと考えています。
つまり、魚にルアーだと認識させない動きやタイミングが非常に重要だということ。
だからこそ、ジグヘッドという針むき出しで到底餌とは言えないルアーで何十年も実績が出続けているのではないでしょうか。
ジグヘッドのスイミングは波動やブレードの光やルアーの視覚的効果と言った針やオモリの存在を惑わす効果があります。
こうして魚を騙して釣るのがルアーの本質的な部分なのかもしれません。
今回の針のサイズは小さめが良いという内容で記載していますが、視覚的な部分も考慮してより魚から見えなくするという意味でフックサイズをダウンさせることは有効ではないかと思っています。
ちょっとしたことですがね。笑
最後までご覧くださり、ありがとうございます。
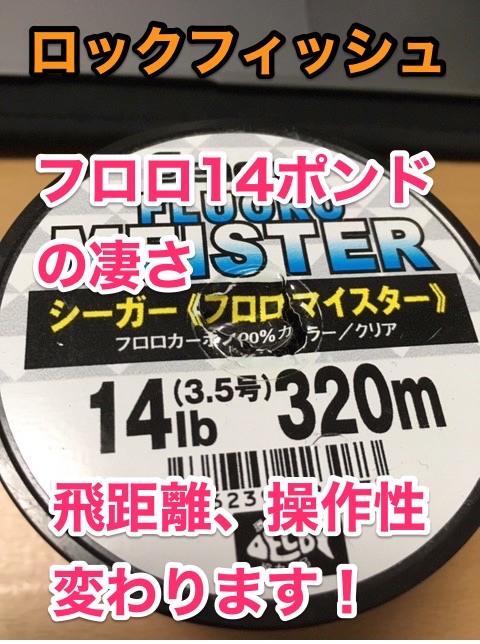
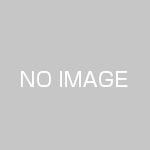




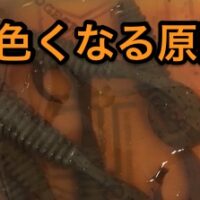
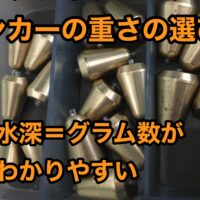
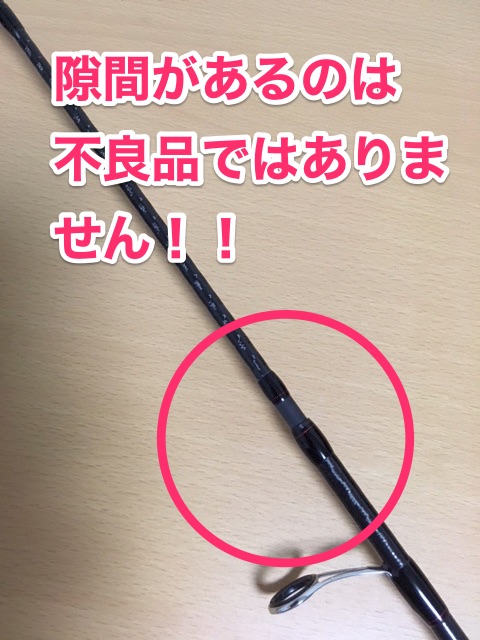
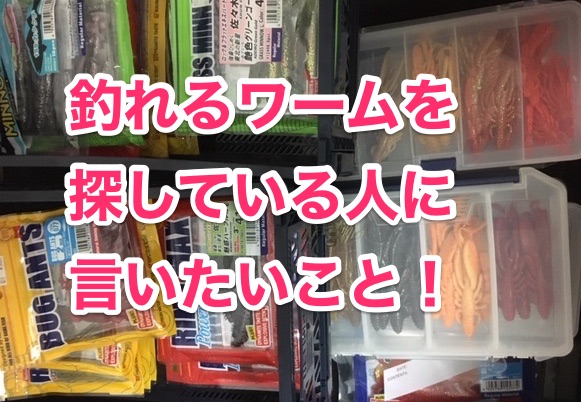



この記事へのコメントはありません。